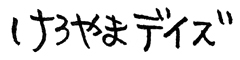その昔、実家には猫がいた。
私が高校のとき、妹が子猫を拾ってきたのだ。
ちょっと毛の長い、雑種のメス。
どうしようもないので一晩泊めたら、ストーブの上に飛び乗って足の裏をやけどしてしまった。
運命は決まった。
名前は「ポチ」。母が決めた。
とはいえ誰もそう呼ばず、「ぽー!」「ぽっぽちゃん!」「ぽっぽこ!」
「ぽ」のつく名前にはたいてい返事した。
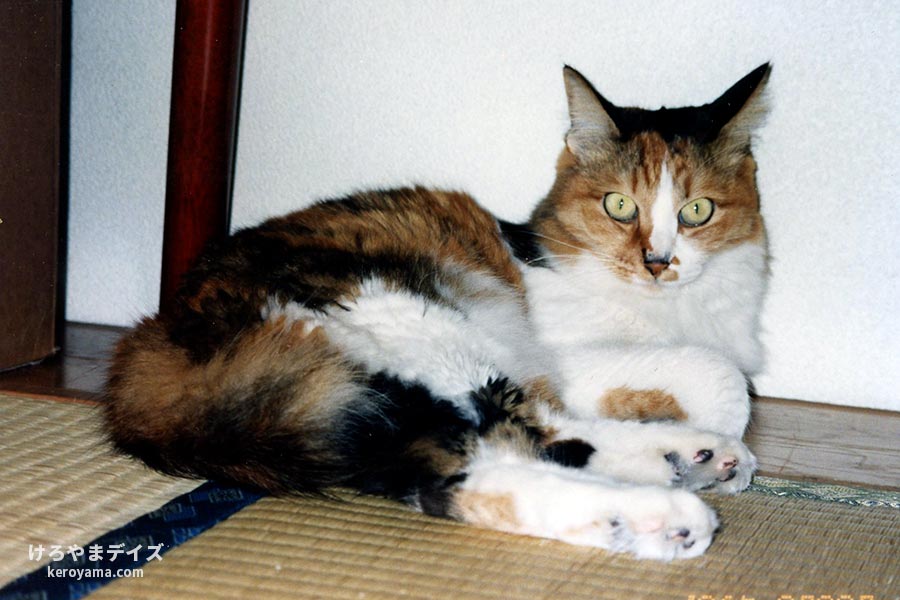
ぽーは抱っこ猫だ。
1日3回、「だっこしろ」「だっこしろ」「だっこしろ」と鳴いてねだる。
早朝でも深夜でもお構いなしだ。
そのくせ、満足するまで抱っこされると、飽きてどこかへ行ってしまう。
ぽーにとって「抱っこ」とは何だったんだろう?
生命の維持にはまるで関係なさそうなのに。

両親がシンガポールへ行くと、1カ月もの検疫での隔離を経て、一緒に現地で暮らした。
4階から転落して骨折もした。
南国の風が心地良いコンドミニアムのベランダに、ネットがかけられた。




ぽーは父や母と性質がよく似ていた。
人の持つ磁力のようなものがシンクロするのか、「この家のメンバー」という顔をしていた。
ぽーがいたころの母は、ちょうど今の私くらいの歳だっただろうか。
学費を捻出するためにフルタイムで働き、いつも床で寝ていた。
あるとき「タロットで占ってほしい」と言われ、そうしたことがある。
母はその頃、何か行き詰っていたのかもしれない。
猫はただいるだけでいい。
抱っこしてお茶をすする。
ぽーの磁力がシンクロして母の心に溶け込む。
猫にそんなつもりはないけれど。
長寿の父の一族に倣ったのか、ぽーも18歳まで生きた。
私は30代で、入院中にその知らせを聞いた。
最後は父と母に見守られながら静かに旅立ったという。
本当は父にも1匹猫がいたらいいのにと思っている。
植木に水をやるように、几帳面な父は猫を大事に大事に育てて、一日中話しかけることだろう。