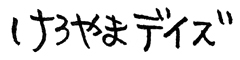私の母は70歳で他界した。
2016年6月の始め、母が末期のがんに罹患していることを知らされた。
父と母は話し合い、抗がん剤などによる積極的な治療を受けないことを選んだ。いわゆる「緩和ケア」、痛みを抑える治療を受けただけだった。
最後の入院までの3か月、母は自宅で過ごした。背中の痛みが強くて外出できず、ほとんどの時間はベッドに横になっていた。
入院してからは3か月。医師より告げられた余命どおり、イチョウが色づく季節に息を引き取った。
病気がわかってから、家族の生活は大きく変わった。
「母が生き甲斐」の父は、少しでも長い時間を母と過ごすことを望んだ。入院した後も時間と体力が許す限り母のもとに通った。高齢の父にとって連日の外出は体力的に辛かったはずだが、ほぼ毎日、休みを取らずに通い続けた。
妹は家事や育児に加えて、仕事の面でもハードな日々を送っていた。それでも運動会などの行事に参加し、そのうえで休日のたびに母に会いに来た。
私はパートで働いていたが、母の病気のことを職場に相談し、勤務を調整してもらうことができた。母が入院してからは、泊りがけで実家と病院、自宅を行き来する日々が続いた。
これから続く投稿は闘病記ではない。
母と一緒にいることのできた半年の間に、私と家族がどのように過ごしたか、何を感じたかを、気持ちの整理のためにまとめていた文章に加筆したものだ。
ほとんどは当時病室で書いた。後になって読むと、粗削りだけど切実で、感情を缶に詰めて密封していたかのように生々しい香りがする。
明るい気持ちになれる内容ではないけれど、あの頃のことを覚えておくために、ここに残します。
(続きはこちら)